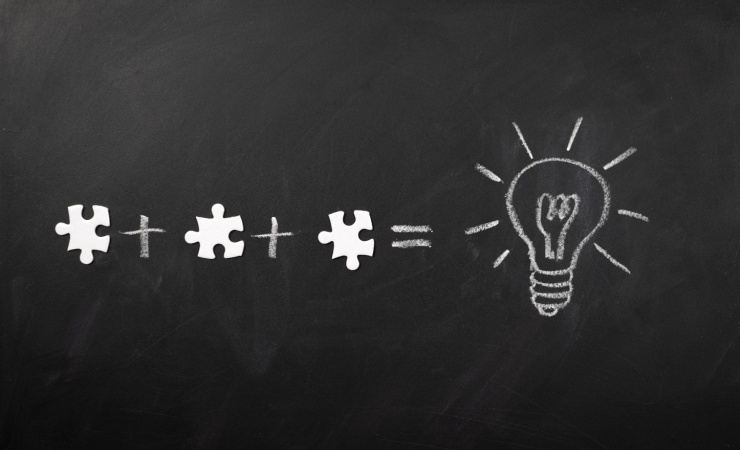はじめに
「海外進出で重要なこと」、2回目の今回は、現地に行かせる人材についてお話ししよう。海外での事業展開を考える際に、多くの企業が間違う点が、「英語が出来る人材」を最優先に探そうとすることだ。もちろん現地に行かせるなら、英語は出来るに越したことはない。しかし、文化慣習や商慣習が全くことなる異国の地において、事業展開を任せられる要の人間の必須要素としては、実は英語の優先順位は低い。なぜなら英語はしょせんツールであり、極論をいうならば言語の問題は通訳や、現地で採用するバイリンガルを配置するなどして適宜補えば、事足りるからだ。
「エース級」の人材
私が海外に派遣する人材として強く勧めたいのは、御社における「エース級」の人材である。ここで言うエース級の定義とは、日本においても事業が生み出せる力がある人間を指す。アイデアが豊富で行動力があり、人を巻き込み結果が出せるという、言わば日本の事業の要であり、日本にも残しておきたいと思えるような人間であるなら、間違いない。

こうした人材は、多くの場合プラクティカルだ。細部にこだわりプロセスを大事にするよりも、時に粗削りであっても結果を出すことの方が、ビジネスでは重要であることを知っている。例え英語が苦手であったとしても、それを補う方法は自分で見つける努力をするだろうし、商慣習上何らかの困難が起こっても、海外と日本の差異を上手に埋める策を見つけられるはずだ。「海外進出した理由は、海外で結果を出すため」という根本軸に立ち返り、海外ビジネスをリードするに違いない。
そんなことを言うと「エース級の人間を手放したら、日本の事業はどうなってしまうのか?」という声が聞こえてきそうだ。しかしそうした不安があるのなら海外展開自体について、再考すべきかもしれない。海外事業の展開を理由に、日本の事業に支障をきたす可能性があるなら、事業計画全体の見直しも必要だ。その海外事業には明確な長期、中期の事業計画は伴っているだろうか。エース級の人材が抜けても、それを補うための社内構造の変革や必要投資などに、経営陣はコミット出来ているだろうか。
「エース級登用」の事例
「エース級登用」で成功した事例の筆頭は、ソニーだろう。同社は1950年代、「自分たちのブランド商品を世界で売る」と覚悟を決め、東京通信工業から世界でも通用するSONYに企業名称を変更した。この試みの第一弾として、北米市場開拓をリードした人間こそが、当時の副社長であり、創業者井深大の右腕でもあった盛田昭夫である。そして彼自身が家族と共にニューヨークに乗り込んだのだ。
「世界で本気で売るのであれば自分がそこにいなければならない」という盛田氏の意思は、北米でのマイクロテレビ販売事業を成功に導いた。そしてこれを機に、SONYは世界ブランドへの階段を上ることとなった。以降同社は、年齢や勤続年数、役職関係なく新規事業にはエースを抜擢するのが伝統となっている。

その他、「エース級登用」で成功した事例は身近にもある。2010年前後、大手新聞社は一斉に電子媒体事業に着手を始めた。当時はまだ紙媒体需要が圧倒的だった時代だ。そのため、ほとんどの媒体が紙事業にエース級を残し、電子媒体を「追加事業」のように扱った。しかしそんな中、日経新聞だけは、選りすぐりのエース級精鋭部隊を集結させ、新規事業に登用したのだ。結果、同社は日本のニュースメディアの有料購読者数という点において、突出した成功を収めるに至った。
日経新聞の電子媒体有料購読者数は、世界規模でもトップである。2017年時点で同社の有料購読者数は50万人を突破。同社は2015年に英フィナンシャル・タイムスを買収しているが、これと合わせると総有料購読者数は114万人になる。これはかのニューヨークタイムスの155万人に続く世界第2位の数字だ。
以上は日本国内の例だが、この成功を前職の関係で自らの目で見てきた経験からも、「新規事業を新規市場で勝負するならエース級を登用」という基準は、私の中で絶対的なものとなっている。未来は不確定であり、海外進出をしても約束された成功はない。その不確定さに臨めるだけの人材登用こそが、海外進出成功への第一歩なのだ。